速読解力検定【速解力】4段認定者インタビュー!昇級・昇段する為の4つの秘訣
公開日:2025.07.02
最終更新日:2025.07.01
この記事は5574文字です。
約5分で読めたら読書速度1200文字/分。
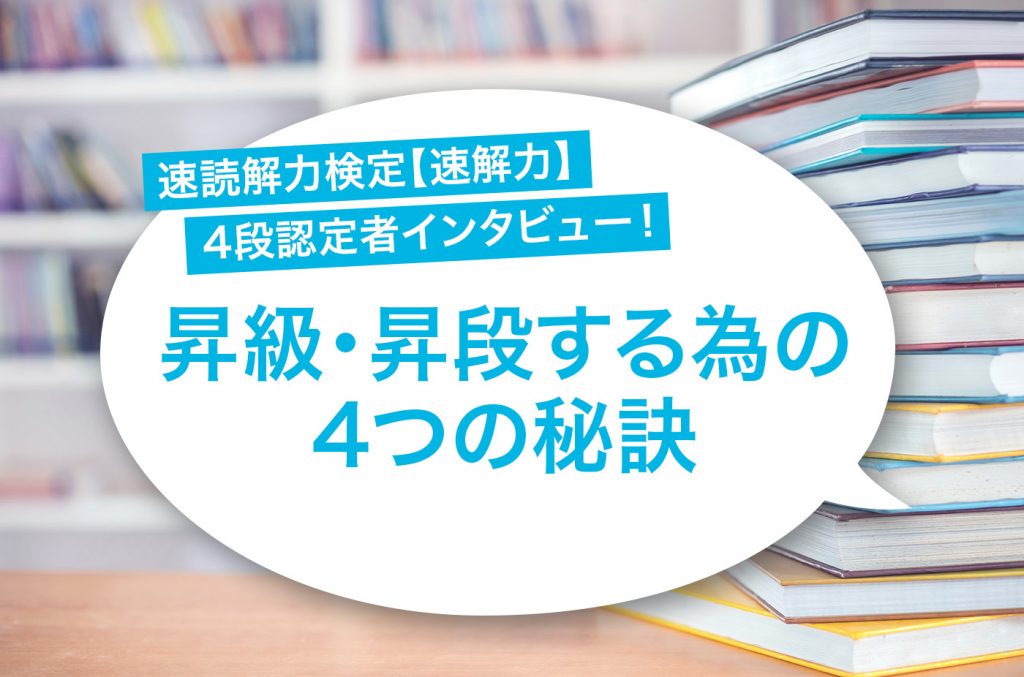
速読解力検定で昇級・昇段を目指す方必見!4段認定者に昇段の秘訣や、普段のトレーニングや気をつけることなどのインタビューを行いました。検定以外のイベントの活用方法や、速解力チェックの高得点のコツなど実践的なアドバイスをお届けします。

インタビュー
Hさん
速読解力検定【速解力】4段
速読解力講座導入教室で、インストラクターを5年務める。最後の1年は速読の専任。
速読甲子園2015年インストラクター部門1位入賞。2017年速解力検定4段認定、1位入賞。現在は株式会社SRJで「速読解力講座」の推進業務に従事。今回、6年ぶりに速読解力検定【速解力】を受検し、4段を取得。
※速解力検定は、2022年に速読解力検定に名称変更しました
目次
速読解力検定で昇級・昇段する為の4つの秘訣

速ドッグロボ

Hさん
1,前回の検定結果を振り返る
まずは、自分の成績がどのくらいだったのか知ることが大切です。前回の個人成績表を確認し、次回の目標を決めて、検定本番に向けて準備をしましょう。
昇級・昇段の認定読解文字数は成績表の裏面にも記載してあります。昇級・昇段したいのであれば、前回より短い時間・高い点数を目指す必要があります。目標時間を決めて、意識しながら本番にのぞみましょう。
<確認ポイント>
- 何分で解いたかを確認する
- 何点だったかを確認する


Hさん
個人成績表は成績画面で確認することができます。

速ドッグロボ
2,速読認定と速解力検定演習を受ける
速読解力検定が無い月に実施される成果確認として、速読認定と速解力検定演習があります。この2つをしっかりと受検し、時間を意識して読み正しく問題を解く練習を行いましょう。
速解力検定演習(4,8,12月実施)
読解速度の目安になります。自分の現在の力を確認して、演習でまずは目標の級・段の読解速度に近づくようにがんばりましょう。
3,たくさんのことに興味をもつ
知らない言葉や知らない題材が出てきたとき、やはり読むスピードや理解度が落ちてしまいます。検定ではどんな内容が出るかわかりませんが、ある程度知っていることについて出てきたほうが読みやすくなります。
そのためには様々な知識があるとその確率が上がります。その手段として、やはり読書がおすすめです。また、出題は、基本的には横書きが説明文、縦書きが物語文です。用語の知識などもあると読みやすくなるので、時事ニュース等にも触れておくとよいでしょう。

速ドッグロボ

Hさん
4,当日受検する時の事前準備
受検は指定月に1回しか受検ができません。年に3回の貴重な機会なので、悔しい思いをしないよう、先生や周りと協力して事前準備をしっかりしてから受検するようにしましょう。
<事前準備のポイント>
- トイレに行っておく
- ネットの通信環境を確認する
- 電池の残量を確認する
- 他のアプリなどの通知が来ないようにする
- 受検することを周りに伝え、話しかけられないようにする

Hさん
問題を読んでから設問に移る解き方で取り組んでください。先に設問を読んでしまうと、読書速度の計測がうまくできません。国語などのテストとは違うので、「速読の試験」として、正しい解き方で取り組みましょう。

速ドッグロボ
4段認定までの受講期間

速ドッグロボ

Hさん
Q.初めての検定では何級を取得しましたか?
大学3年生頃に受けたのが初めてで、初段でした。
認定読解速度は977文字/分、所要時間12分26秒でした。
インストラクターをして3年目くらいのときで、指導は週4回ほどしており、トレーニング自体は2週間に1回30分程度でした。
Q.4段に昇段するまでの訓練期間は?
初回の受検から1年半後、速読を始めてからは5年目です。
認定読解速度は1712文字/分、所要時間6分46秒でした。
4段に向けて、トレーニングは最低でも週1回はしていました。

速ドッグロボ

Hさん
Q.トレーニングをやめても速解力は維持できる?
インストラクターを退職し、株式会社SRJ(日本速読解力協会の運営会社)へ入社後は、ほとんどトレーニングをできていませんでした。今回6年ぶりの受検でも4段に認定されることができたので、速解力は維持できると言えると思います!

おすすめのトレーニング
Q.あえて1~3つだけ挙げるとしたら?
1つ目は、理解しながら読める範囲を広げたいので「識幅拡大・識力向上」です。
2つ目は、読み返した時に必要な場所をすぐに見つけられる検索力です。私が得意なのは「あみだくじ」です。
3つ目は、速さと正確さや短期記憶力、検索力などを鍛えることができる、「速解力チェック」です。

速ドッグロボ

Hさん
Q.速解力チェックで自己ベストを狙うコツ
とにかく全問1回目で正解することです。安定して1回目で全問できるようになったら、次は1問あたりに何秒かけられるかを意識しながら実施します。
たとえば、自己ベストを出したときの所要時間が30秒だったら、次は1問あたり2.5秒を目指して取り組む、という感じです。いろいろな読み方を試しながら、速く読む型づくりができるはずです。
<いろいろな読み方の例>
- 普段読んでいる速度よりもきもち速めに「読めた」を押す
自身の「いつもの速さ」からの脱却、スピードに対する意識向上につながります - 一文ずつ読まずに広く大きくとらえるように読む練習をする
固定読み、2点読みや識幅拡大をイメージして読みます
Q.モチベーションをご自身でどう保っていたのか
得意なトレーニングでの自己ベスト更新など、自分の伸びを実感できるポイントに目を向けてやる気を出すようにしていました。
また、インストラクター時代は、生徒たちと戦って勝つこともモチベーションでした。
Q.直前に対策することはできますか?
速読は「能力」で、日々のトレーニングの積み重ねによって力を伸ばしていくものなので、付け焼刃での対策は難しいかもしれません。
正しいトレーニング方法でコツコツ実施していくことが大切です。
人によってかかる時間は異なるものの、続けてさえいれば必ず速読力は向上が期待できるので、ぜひ諦めずに昇級・昇段を目指してみてください!

速ドッグロボ

Hさん
「やり直し」や「読み返し」は自己ベスト更新を目指す際の一番のタイムロスなので、これを無くすために「一度で正解する」「なるべく一回目で内容を理解して読む」ことが重要なのです。
成績優秀者の声を紹介
小学6年 S.Tさん
トレーニングを始めてから、文章を読むことが速くなっただけでなく、授業の内容が理解しやすくなったと感じています。宿題・課題を短時間で終えられるようになって、テストの見直し時間も増えました。
これから日々の学習はもちろん、入試やスポーツにも鍛えた力を活かしたいです。
中学3年 H.Sさん
初段からの昇級に時間がかかっていたので3段に昇級でき、学年1位を取ることができて嬉しいです。学校では数学の問題を素早く読み、解答する力がついたので総合テストで83点から94点に上がりました。今後控えている高校入試に、今までの速読で鍛えた力を発揮していきたいと思います。
高校1年 S.Mさん
全国1位になったのと同時に3段に昇段することができました。予想外のことだったのでとても嬉しいです。トレーニングを始めてから、特に速く読めるようになったのと短期記憶力が上がったと思います。トレーニングをしたことで県模試で偏差値が60くらいから70になりました。今回の結果を糧に、これからも頑張りたいです。
※成果の表れ方には個人差があります。 ※学年と受講歴は取材当時
速読解力検定は年3回実施
速読解力検定は年3回、全国の「速読解力講座」開講教室で受検することができます。
※受検の実施については、各教室へお問い合わせください。
実施日程
第1回 5月1日~5月31日
第2回 9月1日~9月30日
第3回 1月5日~1月31日
※年度により異なる場合があります。最新の情報は公式サイトでご確認ください
| 構成 | 検定1 速解力(横書き) 検定2 速解力(縦書き) 各 文章1題、設問14問 ※必ず両方受検してください。片方のみの受検は結果の認定ができません。 |
|---|---|
| 制限時間 | 各15分 |
| 問題文字数 | 各2,000~4,000文字程度 |
| 出題形式 | 並び替え、択一、穴埋め、要旨 |
| 受検カテゴリ | 学年により、出題される文章が異なります [ジュニア]小学2年以下 [ベーシックⅠ]小学3・4年 [ベーシックⅡ]小学5・6年 [アドバンス]中学1〜3年 [スタンダード]高校生以上 |

速ドッグロボ

Hさん
資料の中から該当の箇所・単語を探すときなどにも役立っていると思います。
まとめ
普段から時間を意識した読み解く練習をすることが大切
- 前回の検定を振り返り、目標の時間と点数を設定する
- 速読認定と速解力検定演習で、時間を意識して読む・解く練習をする
- 幅広い分野に興味を持つことで知識を増やし、どんな題材でも対応できる力を身につける
- 中断や再受検できないので、事前準備をしっかりとする
速読解力検定は年に3回実施しているので、定期的に受検して実力を確認しましょう。特に級や段が上がってくると、認定されなかったり、昇級・昇段することが難しくなってきます。しかし、速読解力は継続的なトレーニングによって向上する能力です。正しい方法でコツコツと取り組むことが成功への鍵となります。
関連キーワード











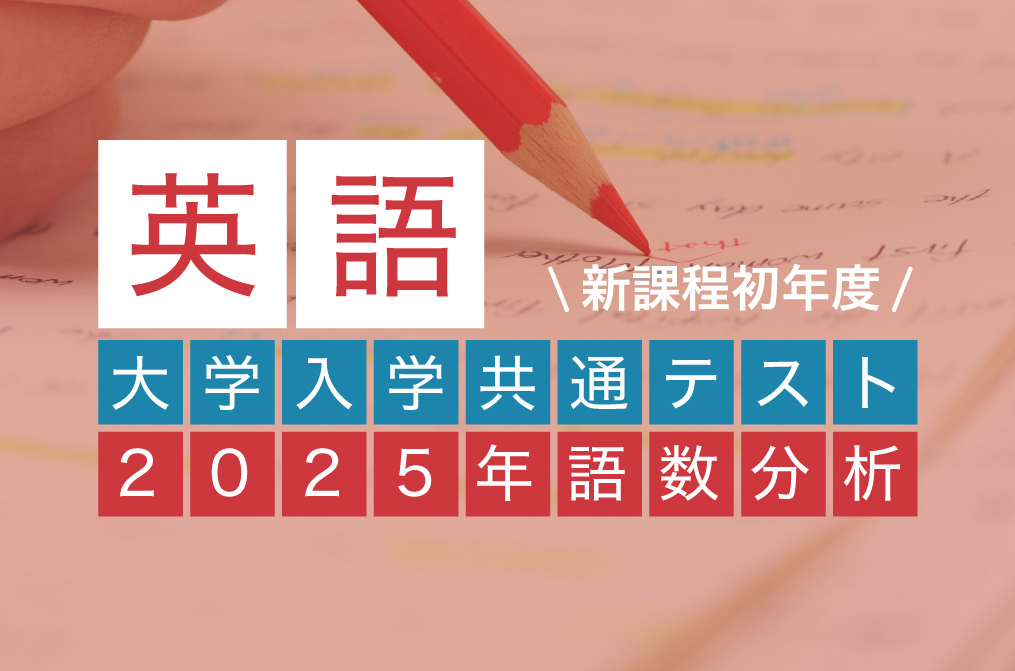
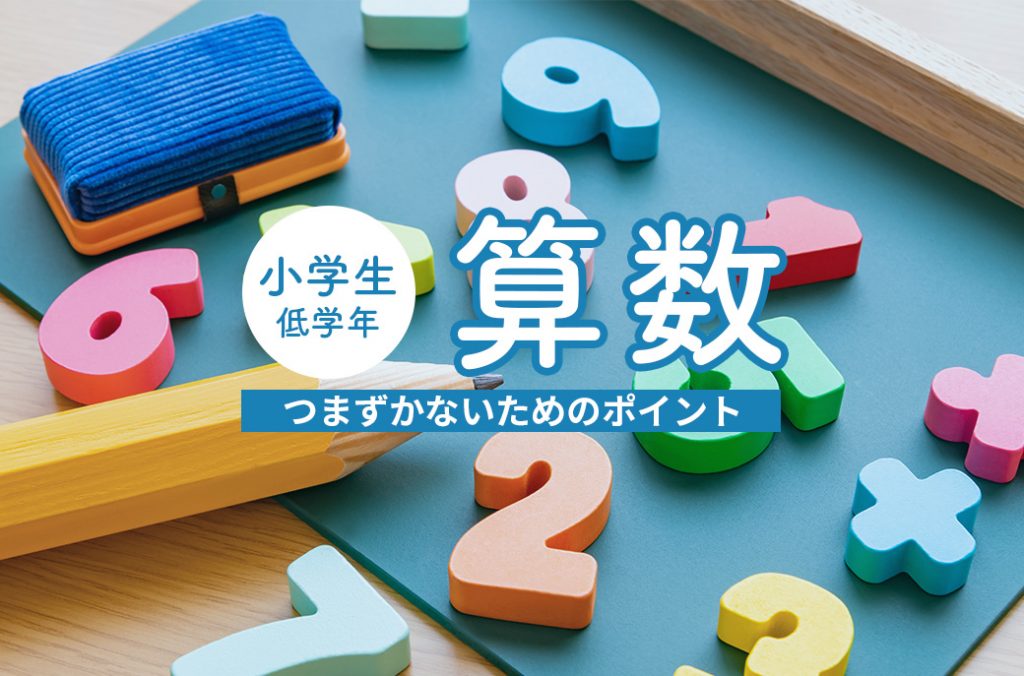
速読認定(6,7,10,11,2,3月実施)
読み返しができないので、1回で内容を理解しながら読む訓練になります。年間の実施回数が多く比較的簡単な成果確認なので、受検を飛ばす人もいますが、昇級・昇段を狙う人は必ず受けてほしいイベントです。