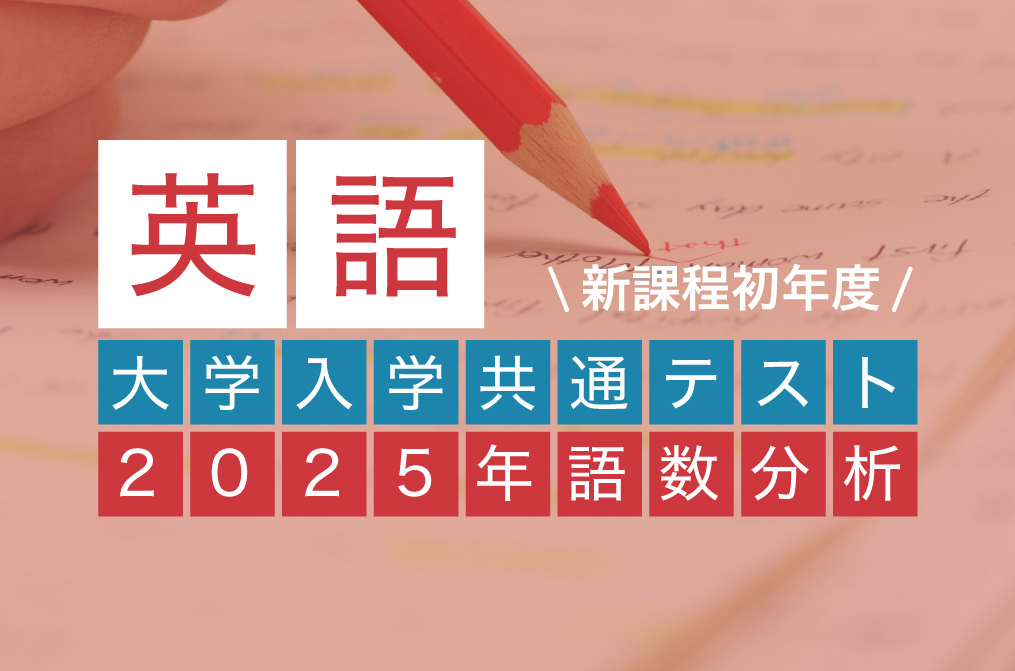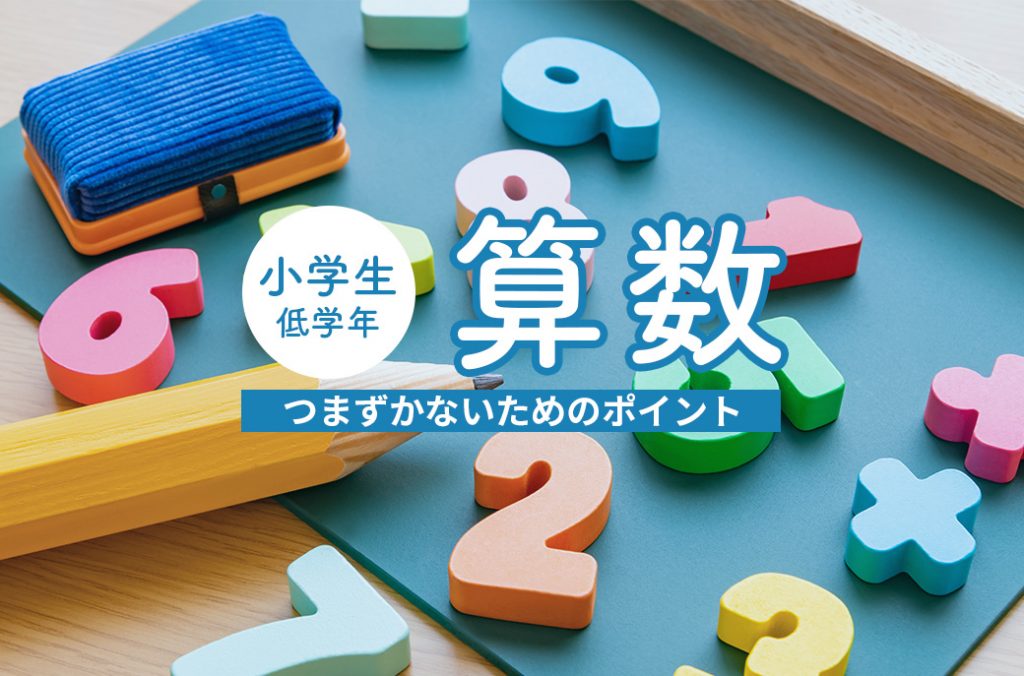小学生の勉強時間はどれくらい?家庭学習を習慣化させるには
公開日:2025.11.17
最終更新日:2025.11.13
この記事は4353文字です。
約4分で読めたら読書速度1200文字/分。

小学生の子どもにとって、家庭での勉強時間は学習習慣を身につける第一歩です。
しかし、「毎日どれくらい勉強させればいい?」と悩む保護者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、小学生の理想的な勉強時間から、家庭学習を習慣にするための工夫など、家庭で実践できる具体的な方法をご紹介します。
目次
小学生の理想的な勉強時間

小学生の勉強時間は、年齢や学年によって目安があります。
疑問を持つ保護者の方に向けて、学年別に解説していきます。

速ドッグロボ
年齢別・学年別の勉強時間の目安とは
子どもの性格や集中力によって集中できる勉強時間には個人差があります。
最初は短時間からスタートし、徐々に増やしていくのがポイントです。
以下は、年齢別・学年別の目安時間を表にまとめたものです。
| 学年 | 年齢 | 目安時間 (無理なく取り組める1回あたりの時間) |
|---|---|---|
| 小学校1年生 | 6~7歳 | 約10〜20分 |
| 小学校2年生 | 7~8歳 | 約20〜30分 |
| 小学校3年生 | 8~9歳 | 約30〜40分 |
| 小学校4年生 | 9~10歳 | 約40〜50分 |
| 小学校5年生 | 10~11歳 | 約50〜60分 |
| 小学校6年生 | 11~12歳 | 約60〜70分 |
これらはあくまで「無理なく取り組める時間」の目安です。
子どもの集中力や生活リズムに合わせて、柔軟に調整しましょう。
重要なのは、毎日一定の時間を継続して学習する「習慣」を作ることです。
「学年×10分」は本当?

小学生の家庭学習の目安としてよく言われるのが「学年×10分」という法則です。
「学年×10分」はシンプルで覚えやすい基準ですが、すべての子どもに当てはまるわけではありません。
集中力が長く続かない子どもには、10分を複数回に分けた学習も有効です。
大切なのは、子どもが無理なく取り組める時間を見つけ、継続することです。
無理に時間を延ばすよりも、子どもが達成感を感じられるような学習を心掛けましょう。
中学受験をする場合に確保すべき勉強時間
中学受験を目指す場合、小学校高学年は平日でも1日2〜3時間の家庭学習が必要になる場合もあります。
宿題や復習に加えて、自主学習の時間を確保するためには、早めに家庭学習の習慣を身につけておきたいですね。
ただし、過度なプレッシャーや押しつけになるような学習時間は逆効果になることもあるので注意が必要です。
適した時間帯の見つけ方

勉強の成果は「いつやるか」でも大きく変わります。
集中力が高まる時間帯や、習慣化しやすいタイミングを知っておくことで、効率よく学習に取り組めます。

速ドッグロボ
集中力が高まるのはいつ?
一般的に、小学生の集中力が高まるのは朝起きて1〜2時間以内で「ゴールデンタイム」と言われています。
この時間帯は脳がリフレッシュされており、新しいことを覚えやすいタイミングです。
特に短時間での学習や、暗記系の内容におすすめです。
ただし、繰り返しになりますが、子ども一人一人の生活リズムによって様々です。
朝起きてすぐに計算問題ができる子どももいれば、読書の方がやりやすいという子どももいます。
朝・夕食前もおすすめ
朝の登校前や、夕食前の時間帯は比較的落ち着いていて、集中しやすい時間です。
「学校に行く前の10分でもいいの?」と子どもは不思議に思うかもしれませんが、もちろん大丈夫です。
「短くても、集中してできれば十分だよ」と保護者が伝えることで、子どもが前向きに取り組めるきっかけになります。
時間を区切ることで、ダラダラせずに集中して勉強することができます。
これが効率的な学習のポイントです。
ただし、無理に時間を固定せず、生活リズムの中で自然に組み込むことが大切です。
生活リズムに合わせた習慣化しやすい時間
「毎日〇時から勉強する」という習慣を定着させるには、家庭ごとの生活リズムに合わせることが重要です。
学校から帰宅後の流れ、習い事の時間、夕飯やお風呂のタイミングと調整して、「この時間は勉強」と体に覚えさせることが継続への近道です。
あわせて、集中しやすい時間帯に何を勉強するか、逆に、集中しにくい時間帯にどういった内容を勉強するか…を組み合わせると、学習効率が上がります。
勉強時間を確保するには
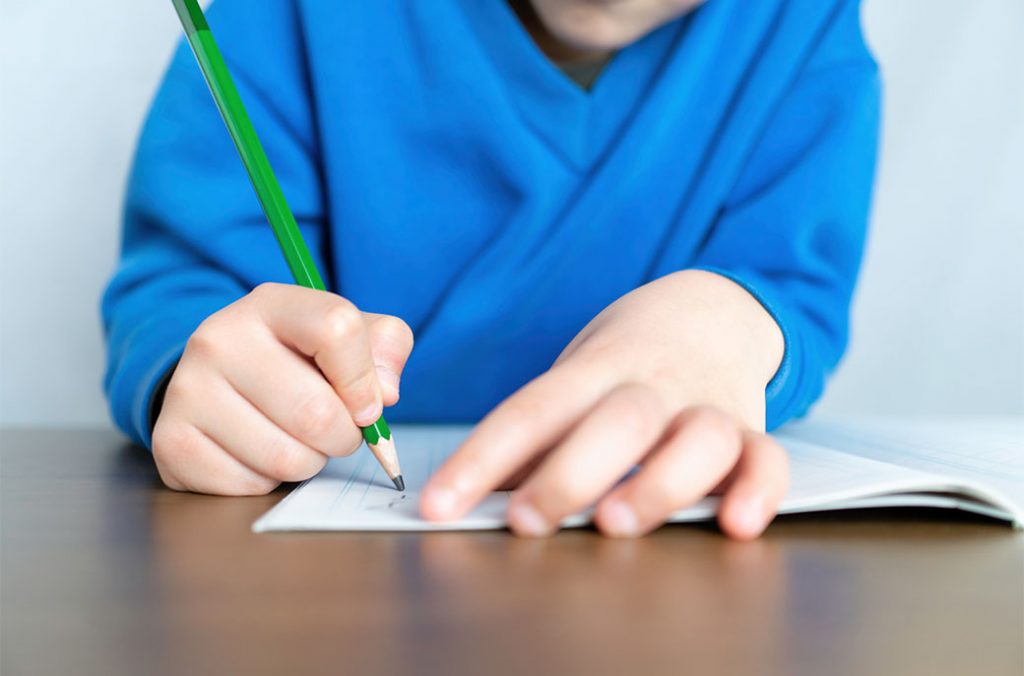
「時間がない」と感じる日常の中でも、工夫次第で学習時間はつくれます。
忙しい家庭でも実践しやすい、勉強時間の捻出方法をご紹介します。
すき間時間を探す・利用する
まとまった時間が取れない日でも、5〜10分のすき間時間は意外と存在します。
学校の準備中や移動中、夕食の支度の合間などに、音読や漢字練習など軽めの学習を取り入れると、すきま時間が自然と積み重なるので、習慣化につながります。
時間を意識する癖をつける
「タイマーをセットして10分だけやってみようか」と声をかけると、子どもは「それならできそう!」とやる気を見せることがあります。
時間を区切ることで、達成感も得やすくなります。
具体的な時間を設定することで、子どもにとって学習のハードルが下がります。
タイマーを使ったり、時計を見ながら学習したりすることで、自分で時間を意識する力も育ちます。
勉強に集中しやすい環境を作る
学習に集中できる環境づくりも大切です。
テレビやスマホが視界に入らない場所、明るく整理された机など、物理的に集中できる空間を整えましょう。
あらかじめ準備をしておくことで「やろう」と思った時にすぐ取りかかれます。
休憩時間も確保することが重要


速ドッグロボ
効果的な休憩を取り入れることで、学習効率がぐんと上がります。
学習の合間にリラックスする時間を持つことで、気持ちの切り替えがしやすくなり、次の学習への集中力もアップします。
子どもの集中力は何分続く?
小学生の集中力の持続時間は、個人差はありますが低学年で15〜20分程度、高学年でも1時間程度が限度と言われています。
それ以上続けると逆に効率が下がるため、適度に休憩を挟むことが必要です。タイミングを見ながら区切りをつけるようにしましょう。
有効な休憩方法とは?脳がリフレッシュする過ごし方
休憩中はスマホやゲームではなく、軽いストレッチや水分補給、ベランダに出て深呼吸するなど、脳をリセットできる方法がおすすめです。
身体を動かすことで脳の血流が良くなり、次の学習にも集中しやすくなります。
小学生で家庭学習を習慣づける重要性
長期的に見れば、家庭での学習習慣は学力の土台を築くだけでなく、将来的な自己管理力や計画性にもつながります。
学習の習慣は、小学生のうちに身につけておきたい力のひとつです。
毎日の取り組みが、自信や学力にどうつながるのかを見ていきましょう。
習慣化がもたらす学力と自信への効果
毎日の家庭学習を習慣にすることで、学力の定着はもちろん、「できた!」という達成感が子どもの自信にもつながります。
一日10分でも継続することが、後々の学習姿勢や自己管理力にも好影響を与えます。
無理なく継続するための声かけ・サポート
「勉強しなさい!」ではなく、「今日はどんなことをやる予定?」と聞いてみてください。
子どもが自分で考え、答えようとする姿勢が自然な学習意欲につながります。
「終わったら教えてね!」という一言も効果的です。
親が一緒に計画を立て、褒めてあげることで、学習がポジティブな習慣として定着しやすくなります。
受験勉強の準備にもつながる
中学受験をしない家庭もあると思いますが、小学生時代に家庭学習を習慣化することは、その先の高校・大学受験に向けた準備にもなります。
日々の学習習慣は、知識の定着だけでなく、時間管理や自己管理を身につけることにもつながります。
これらは非常に重要であり、早い段階で身につけておくことで、受験期には学習計画をスムーズに実行し、ストレスを軽減することが可能です。
小学生のうちから家庭での学習を習慣づけることは、長期的な学力の土台をつくる上で効果的です。
まとめ
最初は短い時間からスタート!
無理なく続けられる時間・タイミングで家庭学習を習慣化しましょう
- 年齢別や学年別の学習時間は目安、重要なのは無理のない時間で継続すること
- 生活の中で勉強に適した時間を見つけて習慣化することが大切
- 習慣化と声かけで継続することに自信を持たせよう
小学生の勉強時間は、「長くやらせる」よりも「習慣として続ける」ことが大切です。子どもに合った時間帯や方法を見つけ、家庭で無理なく取り組める環境を整えてあげることが、将来の学力や自己管理力の土台となります。焦らず、家庭全体で学習習慣をサポートしていきましょう。

監修
安田哲
一般社団法人 日本速読解力協会 理事
約20年間にわたり首都圏大手進学塾の現場の最前線で、英語・国語を中心に指導。中学受験・高校受験の難関校への多数の合格者を輩出。科目の内容の指導だけでなく、家庭学習管理、生徒・保護者の皆様との面談を多数行う。大学院では言語学を専攻、英語以外の言語に関しても幅広い知識を有する。