TERRACE学びFES.第2弾セミナーレポート「10年後、君に仕事はあるのか?」「親子対話の作り方」
公開日:2021.02.25
最終更新日:2021.07.21
この記事は3596文字です。
約3分で読めたら読書速度1200文字/分。
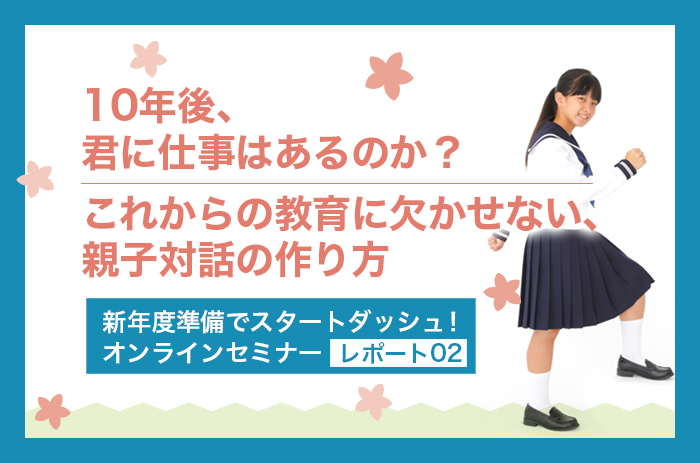
1月17日・31日、TERRACE学びFES.第2弾 『2021年度新中1〜中3必見 親子セミナー「新年度準備でスタートダッシュ!」』がオンラインで開催され、2日間で合計710組の参加がありました。
アンケート結果では「また開催されれば参加したい」の回答が7割以上を占め、大反響でした。
本記事では、藤原和博先生講演「10年後、君に仕事はあるのか?」、江藤真規先生講演「これからの教育に欠かせない、親子対話の作り方」についてご紹介します。
目次
藤原和博先生講演「10年後、君に仕事はあるのか?」
10年後、どういう世の中になっていくだろう
新型コロナウイルスが流行した昨今で、世の中のAI化やロボット化は加速しています。 世界人口の半分以上がスマホを持っていて、いわば世界の50億人と繋がっているような状態。 そして、わからないことは動画で解決できるような時代になっています。
昔は高層ビルが建ったり、新幹線が格好良く速く走るようになったりすることでテクノロジーの進化を感じていましたが、今は「AI・ロボット」の時代で「人間にとって心地よい時代」を作ろうとしていますね。

藤原先生
「情報処理力」と「情報編集力」
まず、10年後を生き抜くためのキーワードとして「情報処理力」と「情報編集力」を挙げます。
- 情報処理力
正解がある問題を速く正確に解く力 - 情報編集力
正解がない(正解がひとつではない)問題に対して、他者の意見も取り入れながら仮説を立て、 自分も他者も納得できる正解を作り出す力
「正解がある問題を解く」という情報処理力が必要とされる仕事は、今後AIやロボットが担っていくことになるでしょう。 しかし、情報編集力が必要とされる仕事は、過去の経験や知識、そして他者とのネットワークからも情報を手繰り寄せて、 正解がない問題を解決に導いていかなければいけませんから、今後も人が担っていくことになります。
そうした想定外の事態に限られた情報の中で対応するという仕事は、これからも人が担っていくことになるでしょう。

藤原先生
そして情報編集力と共に必要とされるのが「基礎的人間力」です。
基礎的人間力というのは、例えば「居てくれるだけで癒やされる」とか「笑顔が素敵」といった、 AIやロボットでは補えられない人間特有のものです。
基礎的人間力が必要な看護や介護といったヒューマンケアレベルの仕事は、これからも生き残っていくでしょう。
稼ぐ大人になりたい
稼ぐ大人になるためには「需要が一定量でも、自分にしかできないことをする」ことです。
仕事も需要と供給で値段が決まります。需要が多い分野で供給が少ない仕事をしたり、自分にしかできない希少性が高い仕事をすることです。
そしてその「稼ぐ大人」に必要なのが、情報編集力です。情報編集力を身につけるには『遊ぶこと』が重要です。
遊びの中からはイマジネーションやクリエイティブが生まれ、情報編集脳が養われます。 また、留学で親の世界観から離れて自分の世界観が築いたり、おじいちゃんやおばあちゃんといった利害関係のない人たちとの『ナナメの関係』を豊かにすることも、情報編集力を高めるために良い経験になります。

藤原先生
江藤真規先生講演「これからの教育に欠かせない、親子対話の作り方」
江藤真規先生
大学卒業後、東京電力株式会社に入社、結婚、退職を経て2人の娘を出産。
自身の子どもたちの中学受験を通じ、コミュニケーションの大切さを実感し、コーチング認定資格を習得。子育ての課題を持つ保護者へのコーチングを展開する。
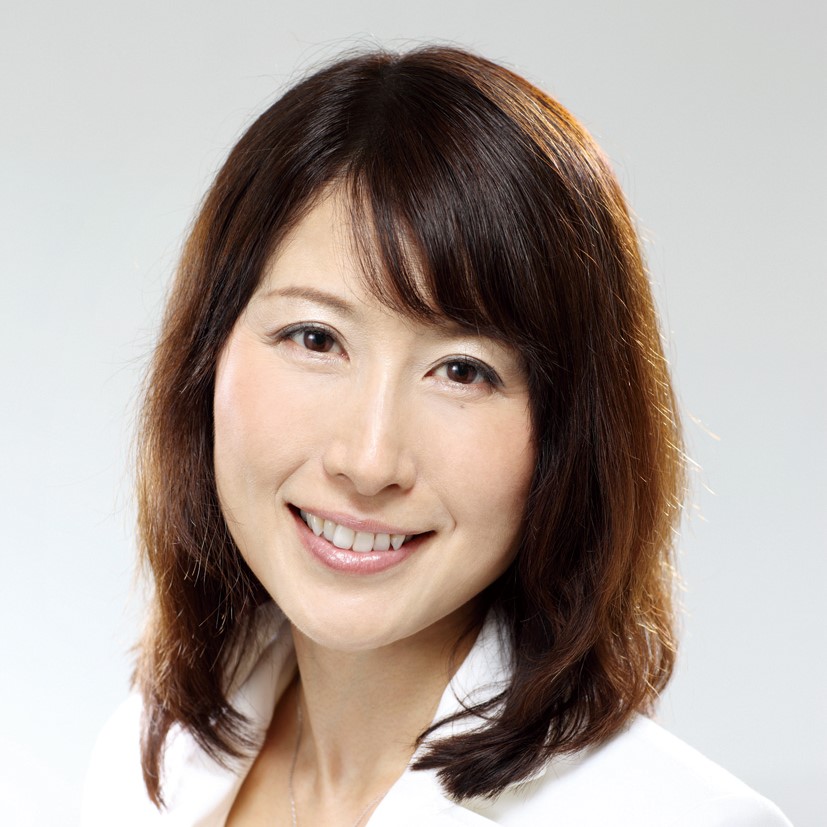
親子対話はなぜ必要か
親の何気ない一言は、子どもに大きな影響を与えます。
例えば、「入試が変わるらしい」という子どもの発言に「不安だね」と答えるのと、「変化にワクワクするね」と答えるのでは受け取り方も全く変わってきます。
親子の信頼関係を構築し、対話を通して子どもを受容・共感・共通理解を示すことは、ストレスマネジメントにもつながります。
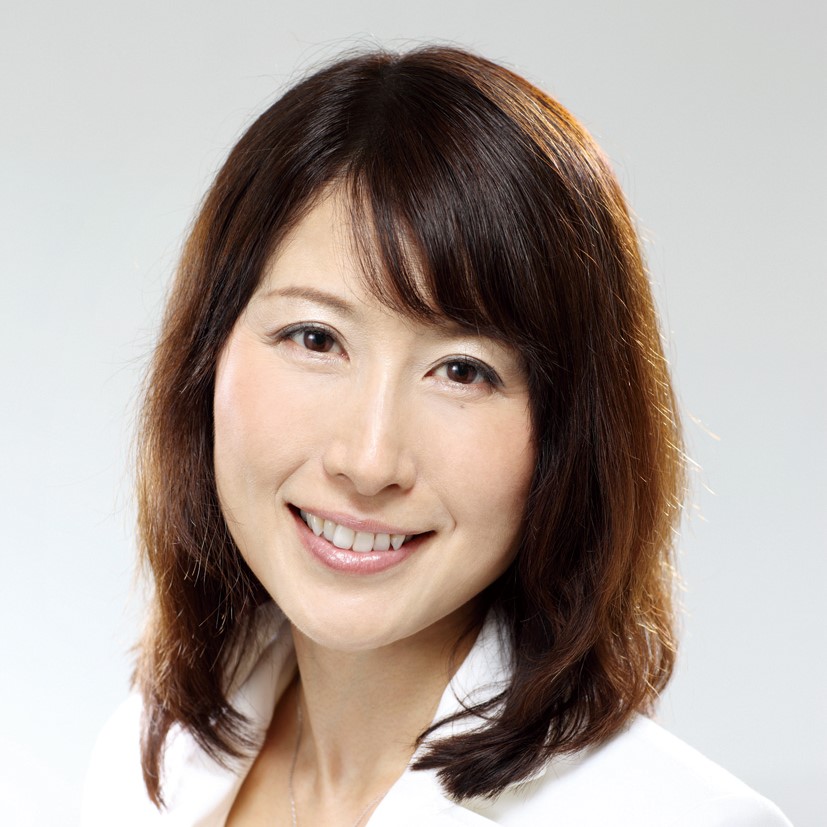
江藤先生
子どもの力を10%上げるための親子対話の作り方
子どものやる気が出ない原因として〝できるかもしれない〟を意識させる部分が置き去りになっているということが挙げられます。
それを解決するために時間軸を意識し、「今月頑張ることを決めよう」「〇〇さんも今の時期は〇点だったらしい」などと声をかけてみましょう。 「他人ごと」を「自分ごと」に置き換える工夫をすることが必要です。
また、子どもの自己分析をサポートし、「強み」を意識させる一方で、子どもの気持ちに寄り添い、受容することを忘れてはいけません。
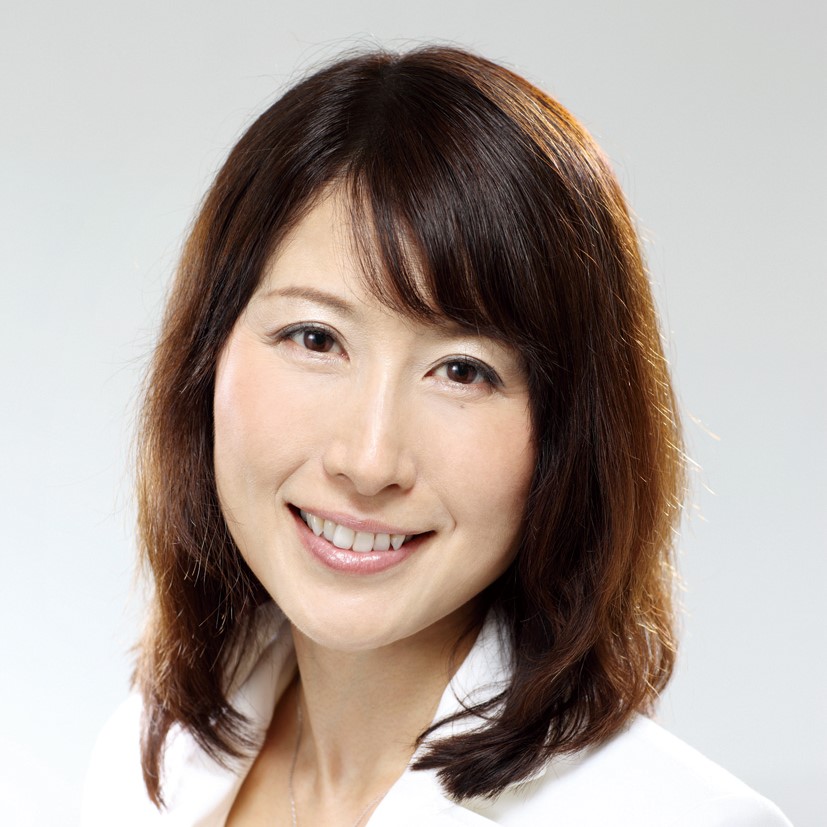
江藤先生
子どもの力(思考力・判断力・表現力)を育むための親子対話の作り方
親子対話を通して、自分自身で考える習慣が身についたり、自身の中にあるものをアウトプットできるようになったりすることで家庭学習の質が高まります。
効果的な親子対話の作り方は3つのステップがあります。
- 子どもの話を聴く
ここで注意したいのが、相手の身になって聴き、理解しようとする〝積極的傾聴〟でなくてはならないということです。例えば、多様な相槌をしたり、子どもの言葉を繰り返したり、言い換えてみたりしましょう。そうすることで、子どもの内省を促し語彙力や表現力が養われます。 - 質問をする
子どもが考えるための質問をすることで、視点を変える、未来をイメージする、目標を設定する、課題を特定するなどの効果を期待することができます。例えば、「一番大切にしていることは?」「なにがあったら上手くいく?」「それは誰が決めること?」「まずは何から始める?」などの質問をして〝気づき〟や〝自己決定〟を促しましょう。 - いっしょに考える
子どもは子どもながらに、その時々で感じることや考えることがあります。子どもだからといって、「まだ分からないだろう「まだ無理だろう」という決めつけをしてはいけません。 子どもと一緒にSDGsなどの社会的課題対して、家庭での身近な対話や自分との対話を通じて、考える習慣を身に付けることが大切です。
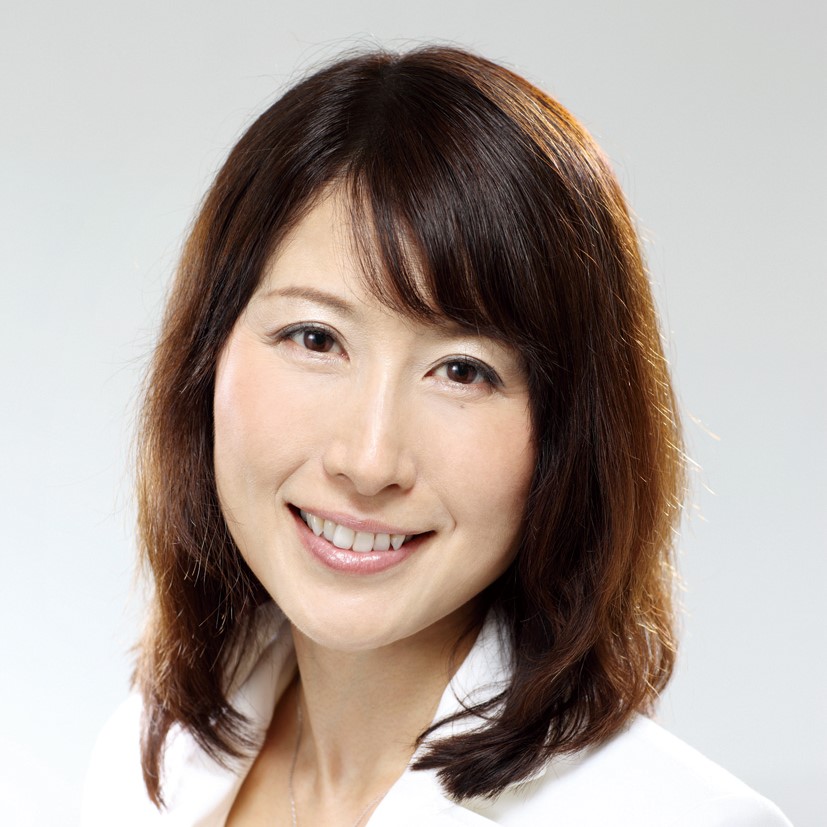
江藤先生
まとめ
イベント内容、募集中!
日本速脳速読協会では、親子で参加できるオンラインイベントが開催できるよう、企画し続けていきます! 「こんな内容が知りたいな」「この先生の話が聞いてみたい」など、皆さんからのアイデアもお待ちしています。 お問い合わせフォームからぜひ投稿してくださいね。









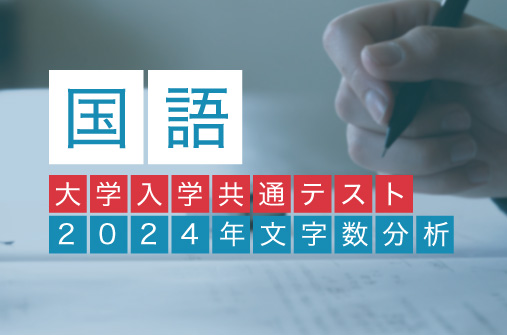
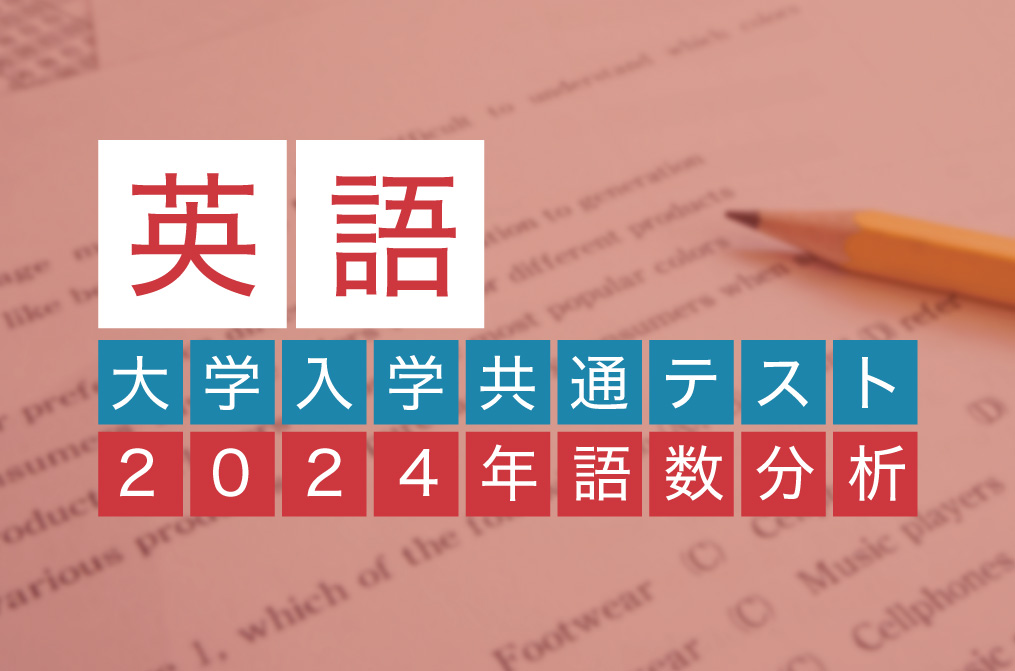
藤原和博 先生
東京大学経済学部卒業後、株式会社リクルートに入社。義務教育初の民間校長として杉並区立和田中学校校長を務め、奈良市立一条高等学校前校長、「朝礼だけの学校」校長。
「人生の教科書作家」とも呼ばれ、中でも、子どもたちには「キミが勉強する理由」がおすすめ。「10年後、君に仕事はあるのか?」(ダイヤモンド社)は、145万部を超える大ベストセラー。